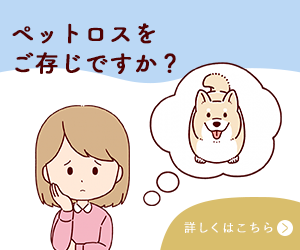近年、獣医療やペットフードの質の向上などによって猫の平均寿命は伸び続けており、15才以上の長生き猫さんも珍しくなくなってきました。
猫の15才をヒトに換算すると70才半ばといわれています。70才半ばといえばヒトでも認知症が気になってくる年齢ですね。
猫においても、長命化に伴い認知症というべき症状があることがわかってきました。飼い猫が高齢になってきて認知症ではないかと心配になっている飼い主に向けて、猫の認知症について解説します。
目次
猫の認知症について
まずは猫の認知症とはどういう症状なのか、何歳からなるのかについて解説します。
猫とヒトの認知症は同じ?
認知症とは、何らかの後天的な脳の障害が原因で認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のことです。主な原因は老化ですが、脳に老廃物が蓄積して神経細胞を傷害することで脳全体が萎縮するアルツハイマー病や、脳疾患や全身疾患に伴う場合があります。
また、ヒトに比べると発生頻度は高くありませんが、脳血管障害により認知機能の低下が見られることもあります。高齢猫で多い慢性腎臓不全や甲状腺機能亢進症という病気は、二次的な高血圧を起こしやすく、脳血管障害を起こすリスクが高くなります。
猫は何歳から認知症になるの?急になることはある?
10歳を過ぎる頃から認知機能の低下が見られる猫が増加し、15歳以上になると半数程度の猫に何らかの認知症の症状が見られるといわれています。
猫の認知症を疑う行動とは!?チェックリストで確認しよう!
猫の認知症を疑う最も重要なポイントは「今までと異なった行動の出現」です。
認知症によってあらわれる行動の変化はさまざまであり、普段から一緒に暮らしている猫の様子に変化があれば、ちょっとした違和感を覚えるはずです。
その違和感を「歳のせいかな」などと自己判断して放置しないことが重要です。そのことをふまえたうえで、認知症の猫で代表的と思われる症状を紹介しますのでチェックしてみてください。
- 無駄鳴き、夜鳴きの増加
- トイレの粗相が増える
- 徘徊行動をする
- 性格や食事などの好みが変化する
- 活動性が低下し、寝ている時間が長くなる
認知症かな?と思ったらとるべき行動!

認知症かな?と思い込み、病気を見過ごしているケースが非常に多くみられます。自己判断せずに、まずは動物病院に相談することが大切です。
動物病院で認知症かの検査を受ける
猫の認知症に関する研究はまだ始まったばかりであり、ヒトの認知症との違いなども含めてまだまだわからないことが多い領域です。現在の獣医療では、認知症を直接診断するための検査や基準は確立されていません。
あらわれている症状から疑われる他の病気の可能性を全て検査で除外し、「認知症」という結論にたどりつきます。
認知症の代表的な症状が、実は病気が原因で出現していることもあります。
以下に、具体例をあげます。
| 症状 | 代表的な病気 |
|---|---|
| 無駄鳴き、夜鳴きの増加 | 甲状腺機能亢進症、高血圧症、脳腫瘍 |
| トイレの失敗 | 下部尿路疾患(膀胱炎など)、運動器疾患、関節疾患 |
| 異常な食欲 | 甲状腺機能亢進症、糖尿病、腫瘍 |
| 性格の変化(攻撃的になるなど) | 甲状腺機能亢進症、脳腫瘍、関節疾患などによる痛み |
ざっとあげただけでもこれだけの病気が考えられます。自宅で観察するだけでこれらの病気を認知症と見分けることは不可能です。くれぐれも自己判断はしないようにしましょう。
動物病院で必要な検査は症状によってさまざまですが、尿検査や血液検査などの麻酔の必要がない比較的手軽で安価な検査だけで診断がつく場合も多くあります。
一方、脳腫瘍を疑う状況などではCT検査やMRI検査が必要になることもありますが、費用や全身麻酔のリスクを伝えた上で、どこまで検査を実施していくかも含め、獣医師とよくコミュニケーションをとりながら進めていきましょう。
認知症の治療法はあるの?
猫の認知症については、まだまだ研究が始まったばかりであり、残念ながら治療薬は開発されていません。
認知症という結論がでたら……改善することはあるの?自宅でできる対策や予防法とは

動物病院で検査を行ったが病気は見つからない……認知症だろう。そんな結論にいたったならば、飼い主はどのような対応をとればいいのでしょうか。
生活環境を整える
認知症の愛猫のために適した生活環境を整えてあげましょう。
- 老猫はある程度家具や家の配置を記憶しているため家具の配置を変えない
- 猫が移動をするスペースに物を置かない
- 猫がぶつかる場所にクッション性のあるものを設置する
- キャットタワーなどは段差の少ないものにする
- フローリングなどの滑る床にはマットを敷く
夜鳴き(夜泣き)や粗相などの問題行動への対策をする
トイレの失敗が多いようであれば寝床のすぐ近くなど複数箇所にトイレを置くことが有効な場合もあります。認知症の猫では運動機能も落ちていることが多いですから、あまり縁が高くないトイレを用意してまたぎやすくしてあげることも一つでしょう。ご飯を貰ったことを忘れて夜中に起きだしてくるようであれば、自動給餌器を活用する方法もあります。
ただ、夜鳴きは家族だけでの対応が難しいこともあります。家族の日常生活に支障が出ている場合には、内服薬を処方してもらうよう獣医師に相談してみましょう。
サプリメントも一つの手段
少しでも症状が進むのを防ぐために、認知症の猫のためのサプリメントを試してみるのも一つかもしれません。
DHA・EPAやビタミンEなどの抗酸化成分を積極的に摂らせることは症状の進行を遅らせる可能性があるとされています。ただし、サプリメントの効果に関してもまだまだ研究途上ですから、効果があれば嬉しいくらいの心構えがいいかもしれませんね。サプリメントも獣医師に相談した上で試すようにしましょう。
まとめ
老猫ともなれば、認知症になる可能性は出てきます。今までと異なった行動を起こしたり違和感を感じた場合、「歳のせいだろう」で済まさずに動物病院に相談してみましょう。
最も大切なことは、ヒト側が愛猫の認知症を受け入れて、いかに双方がストレスなく寄り添いあっていけるか考えること。猫の行動を治療によって変えようとするのではなく、猫もヒトも双方がストレスを受けづらいような環境を、ヒト側で整えること大切です。
愛猫との楽しい時間を増やすために、飼い主としてできる対策を考えていきましょう。