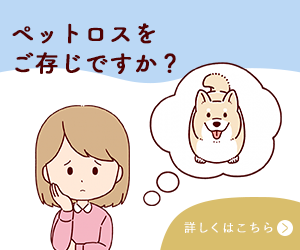人間だけではなく、犬や猫など多くの生物が生命を維持するために欠かせない機能の1つが「呼吸」です。その呼吸が異常をきたしている場合には、特別な注意が必要であり、ときにはわずかな治療の遅れが生死をわけることもあります。
この記事では、老犬の犬の息が荒い、呼吸が早い場合の正常な呼吸と異常な呼吸の見分け方、原因、対処法や治療、お家でできることなどについて解説します。
目次
老犬の息が荒い?呼吸が早い?具的な兆候と症状について
一言で「息が荒い」や「呼吸が早い」といっても、正常か異常かはどのように見分ければ良いのでしょうか?ここでは、正常な呼吸と異常な呼吸の見分け方、具体的な兆候と症状についてみていきましょう。
呼吸の回数が多い(呼吸が早い)
「息が荒い」や「呼吸が早い」と感じた時には、愛犬の正常な呼吸数と比較してみましょう。
一般的に、成犬の安静時の正常な呼吸数は1分間に10~35回程度です。ただ、小型犬は比較的多く、大型犬は少ない傾向があるため、愛犬の正常な呼吸数を把握しておきましょう。
呼吸数のカウントは、「吸って吐いて」の1セットが1カウントです。愛犬がリラックスしている時にお腹の動きを見たり、からだにそっと手を添えたりしてカウントしましょう。
犬の呼吸を1分間ずっと数え続けるのは難しいため、10秒間でのカウントを6倍することがおすすめです。涼しい環境で1分間の呼吸回数が40回以上の場合や、正常時より呼吸数が多い場合には異常といえます。
呼吸状態がおかしい
回数は多くなくても、以下のようにあきらかに呼吸状態がおかしいときには、すぐに動物病院に連絡をして一刻も早く受診しましょう。
・苦しそうな様子をしている
・口を開けて呼吸する(開口呼吸)
・のけぞるように上を向いて呼吸している
・呼吸音が大きい
・ヒューヒューやガーガーといった異常な呼吸の音がする
・舌の色が白色や紫色になっている
老犬の息が荒いまたは呼吸が早いときに飼い主ができる対処法

まず大切なことは、飼い主の自己判断で「様子をみない」ことです。呼吸の異常が見られたら、できる限り早く動物病院へ連れて行きましょう。呼吸の異常は、治療開始の遅れがそのまま生死をわけることもあります。したがって様子をみるにしても、一度しっかりと獣医師に相談をして「様子をみても大丈夫でしょう」という判断をもらってからのほうが安心です。
動物病院へ連れて行く際に注意したいこととして、以下の点が挙げられます。
・楽な姿勢にさせる(基本的に犬はうつぶせが呼吸しやすい勢です)
・興奮させない
・胸やお腹を圧迫しない
・なるべく涼しく、湿度も低く保ちながら移動させる
これらは呼吸状態をさらに悪化させないように必要なことです。
また、真夏に空調をつけていなかったために熱中症が強く疑われる状況であれば、犬を涼しい場所に連れて行き、からだを常温の水で濡らしたり、首や脇をタオルで巻いた保冷剤で冷やしたりなど体温を下げる応急処置をとりましょう。このとき、氷水を使わず、必ず常温の水をかけることが重要です。
老犬の息が荒いまたは呼吸が早いときに動物病院で行われる治療法
老犬の息が荒い、呼吸が早いときに動物病院で行われる治療法を紹介します。
原因に対する治療
呼吸状態が悪くなっている原因を取り除くための治療です。
例えば、胸水の貯留が原因の場合は、穿刺で貯留液を抜き取る処置を行います。また、気管支炎や肺炎の場合には、抗生物質や抗炎症剤の投与などを行います。
さらに、持病があり、その悪化が原因と考えられる場合には、それぞれの疾患の治療を行います。
呼吸状態を緩和させるための治療
原因を取り除くのが難しい場合は、原因の治療と並行しながら、少しでも呼吸を楽にして息苦しさを和らげてあげる治療を行います。
ICUケージや酸素室で空気よりも高濃度の酸素を吸わせ、低酸素状態になっている組織に酸素を供給し、「息苦しい」という症状を和らげる酸素療法を行います。
また、対症療法として呼吸が楽になるように気管支拡張剤や鎮咳剤、去痰剤、ステロイドを含む抗炎症剤などを投与します。
老犬の息が荒いまたは呼吸が早いときの原因(病気以外)

呼吸の異常はさまざまな原因によって引き起こされます。
ここでは、老犬の息が荒い、呼吸が早いときに考えられる原因を病気以外と病気の場合に分けて解説します。まずは病気以外に考えられる原因をみていきます。
老化によるもの
犬も年齢を重ねると、身からだの中のさまざまな機能が低下し、筋力や心肺機能が衰えます。成犬の時は平気だった散歩や運動などでも、少し走っただけでも疲れやすく、ハァハァと息切れを起こしやすくなってしまいます。これは、加齢による身体機能の低下が原因であり、特に問題はありません。
また、認知機能が低下し、認知症になると本人の意思では止まろうと思っても止まれないため、ときおり息が上がりハァハァと言いながらも一定方向に回り続けてしまうことがあります。その他にも認知機能の低下から、部屋の隅から動けなくなる、昼夜が逆転して夜中に吠えるなどさまざまな行動がみられます。
体温調整のため
犬は人間のように皮膚に汗をかくことにより、からだ温調節を行うことはできません。犬は口を開けてハァハァと呼吸する「パンティング」で体温調節を行います。パンティングは、運動時や暑い時などに見られる生理現象のため問題はありません。
しかし、なかには熱中症のようにパンティングを伴う病気もあるため、安静時や涼しい環境においても犬がパンティングを行っている場合は注意が必要です。
不安やストレスのサイン
犬は恐怖、緊張、不安などの精神的要因から交感神経が優位になり、一時的に呼吸が荒くなります。時間が経過したり、原因が取り除かれた場合、呼吸が落ち着くようであれば、不安やストレスが原因の可能性が高いと言えます。
痛みがある可能性も
からだに痛みがある場合にも、息が荒くなることがあるのです。あまり動きたがらない、震えなどの症状も一緒に見られれば、何処かに痛みがある可能性が考えられます。
老犬の息が荒いまたは呼吸が早いときの原因(病気の場合)
次に、息が荒い、呼吸が早いときに原因として考えられる病気を解説します。
獣医師は聴診や視診などの身体検査で大まかに原因の予測をつけて、その後の検査や治療の方針を立てていきます。
鼻の異常:鼻炎など
鼻の内部に細菌などの感染症、アレルギーなどが原因で炎症が起きてしまうと息が荒くなる可能性があります。症状としては、くしゃみや鼻水が見られ、重症化すると鼻の内部が腫れてしまい、呼吸がしにくくなる場合もあるのです。
のどの異常:軟口蓋過長症など
のどに起こる異常としては、軟口蓋という上あごの後方にのびた柔らかい部分が通常よりも長く垂れ下がり、気道を塞ぐことで、空気をうまく吸い込めなくなる「軟口蓋過長症」という病気があります。
「のど」はいわば「気管の入り口」であり、そこに異常が生じて空気をうまく吸い込めなくなることがあります。特に、パグやフレンチ・ブルドッグに代表される短頭種で多く発生します。適切な処置により苦しさが軽減することも多いですが、重症化すると粘膜が紫色になるチアノーゼや呼吸困難を起こし、命に関わる場合もあります。
気管の異常:気管虚脱、気管支炎など
気管の一部がつぶれて異常に狭くなり、呼吸が妨げられる病気を「気管虚脱」といいます。特に小型犬で多く、症状としては息を吸うときに、ガーガーという雑音がします。この病気は進行性であり、重症化すると粘膜が紫色になるチアノーゼや呼吸困難を起こすことがあります。
その他に、咳の症状がみられる気管支炎などが問題となることもあります。
肺の異常:肺水腫、肺炎など
吸い込んだ空気から酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する重要な機能を担っているのが肺です。肺に異常が生じて、その機能が果たせなくなると「息が荒い」という症状が出てきます。
肺の異常で代表的なものは、「肺水腫」と「肺炎」です。特に、肺水腫はその大半が心臓病によって引き起こされます。心臓病になると、心臓が正常に働かないことで、肺に水が溜まるのです。また、肺炎の多くは感染性のもので、咳や発熱、食欲がなくなるかどの症状が見られ、重症化すると死に至ることもあります。
胸腔内の異常:胸水など
胸腔とは、わかりやすくいえば肋骨に囲まれて心臓や肺が収納されている空間のことです。この空間内に異常が生じると、肺の拡張が制限されることがあります。その異常として代表的なものが、血液や漿液などの液からだ成分がたまる「胸水」です。その他、気胸や横隔膜ヘルニアといった病気も原因となります。
心臓の異常:僧帽弁閉鎖不全症など
中高齢の小型犬に多く見られる「僧帽弁閉鎖不全症」は心臓の左心房と左心室の間にある心臓弁である僧帽弁がきちんと閉じなくなり、心臓内で血液が逆流してしまい循環不全を起こす病気です。運動したり興奮したりすると咳の症状があらわれ、悪化すると呼吸困難に陥ります。
その他には、フィラリアという寄生虫が心臓や肺動脈(心臓と肺の間の血管)に寄生する「フィラリア症」や、大型犬に多くみられる「拡張型心筋症」なども原因となります。
その他
貧血や熱中症などの病気も原因となります。
まとめ
「呼吸」という営みは生命維持の根幹です。そこに異常をきたしている場合には、緊急度が高く命に関わることが多くあります。原因はお伝えしたようにさまざまであり、自宅で判断することは困難です。
受診・治療の遅れが生死をわけることも少なくありませんので、なるべく早く動物病院を受診するようにしましょう。