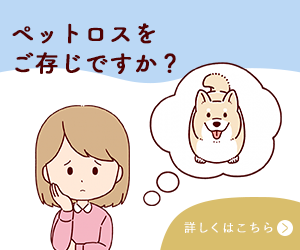愛犬の様子を見ていて「老衰が近いのかもしれない」と不安を感じることはありませんか?また大切な愛犬が老衰を迎えたら、どうすればいいか不安になっている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
老衰について知っておくのはつらいことですが、最後まで犬が幸せに過ごすためにも大切なことです。
本記事では、犬の老化現象や老衰期に表れる症状や飼い主にできることについて、くわしく解説します。
目次
犬の平均寿命

まず、犬の平均寿命について把握しておきましょう。最近では医療や食事の品質が向上しているため、年々、平均寿命は伸びています。
「アニコム家庭どうぶつ白書2022」によると、犬全体の平均寿命は2020年の時点では14.1歳です。
大型犬の平均寿命は10歳ほど、中型犬は11歳~13歳ほど、小型犬は11歳~15年ほど、超小型犬は13~15年ほどであり、小さいサイズの犬種の方が平均寿命は長いという統計が出ています。
関連記事:犬の平均寿命って何歳?健康寿命を伸ばす秘訣を紹介!
老衰した犬にみられる症状とは

犬の老化現象にはさまざまなものが見られます。体調不良のこともあるので、一度かかりつけの動物病院で診てもらうのがおすすめです。
睡眠時間が増加した
活動量が減り、寝ている時間が増えてきます。睡眠が昼夜逆転してしまい、夜吠えることもしばしばです。寝ているときは、起こしてもなかなか反応しなくなることもあります。
遊びに消極的になった
遊びに誘っても、乗り気になってきません。好きだった遊びにもあまり喜ばなくなり、興味が薄れてきます。仲が良かった他の犬が来ても、はしゃぐこともなくなっていきます。
散歩時のペースが遅くなった
以前のように元気に歩いたり、走ったりできなくなります。そのため散歩のペースも遅くなってしまうのも、老化現象によくみられる症状です。階段の上り下りを躊躇したり、よぼよぼ歩いたりしている場合は、椎間板ヘルニアや関節疾患などの痛みなどがないか受診も必要です。
食事量が減ってきた
活動量が減る分、食事量も減ってきます。食欲が落ち、食べたり食べなかったりと食べムラが見られることも。口内炎や歯のトラブルがないかチェックが必要です。
口臭がきつくなった
唾液の分泌が減少するため、口臭を感じることが多くなります。口臭の原因が、歯周病や口内炎などの場合もあるので必ず診察を受けておきましょう。
老衰した犬の死ぬ間際の兆候
年を取って老化が進んでいくと、どうしても弱っていきます。老衰の末期症状になると、愛犬の旅立ちが近いと考えていいでしょう。ここでは、老衰した犬が亡くなる直前にみせる前兆を解説します。
食事も水分も摂らない
食事も摂らなくなり、水も受け付けなくなっていきます。スポイトなどで流動食やお水を口に入れても、飲み込むことができません。
意識が朦朧とすることが増える
寝ているのではなく、意識がないような状況です。呼吸が乱れ、名前を呼んでも反応がほとんどなくなり、目を開けることもほとんどありません。また目を開けていても、どこを見ているかわからない状態です。
体温が低下する
老犬になると、体温調節がうまくいかなくなりがちです。末期症状になると、だんだんと体温が低下してしまいます。
痙攣を起こす
死が近づくと痙攣やふるえを起こすことがあります。足をばたつかせるため、飼い主はびっくりすると思いますが、慌てて無理に押さえつけないようにします。対応がわからない場合は、獣医師に相談しましょう。
死ぬ間際の犬が挨拶をすることもある

亡くなる直前に、愛犬が飼い主に挨拶をするというケースもよくあります。ここでは、よくある2つの挨拶について紹介します。
ご紹介する愛犬の行動を「最後の挨拶」の可能性があると知っているかどうかで、飼い主の対応が変わるかもしれません。
もし、飼い主が愛犬の行動の意味をわからないまま接してしまい、その直後に亡くなってしまうと、後悔につながり、深刻なペットロスに陥る可能性もあります。
愛犬が亡くなる間際に挨拶することがあるということを、頭のどこか片隅に置いておくと、後悔のない対応ができるようになるでしょう。
飼い主に向かって鳴く・尻尾を振る
亡くなる間際の犬は、一般的に元気がなく、静かにしています。そんな中で、突然飼い主に向かって鳴いたり、尻尾を振ったりすることがあります。
残った体力を振り絞り、最後に飼い主に向かって「ありがとう」と挨拶したケースといえるでしょう。
飼い主に甘えてくる
あまり甘えたことがない犬が、飼い主に甘えてくることがあります。これまでと異なる行動を取るのは、最後に飼い主の温もりに触れたかったのかもしれません。愛犬が寂しくならないよう、できる限り甘えさせてあげましょう。
老犬に飼い主ができる6つのこと

老衰期を迎えた愛犬には、介護が必要です。愛犬のために、飼い主ができる6つのことをご紹介します。
床ずれ防止のための体位変換
老衰ではほとんどの場合、犬は寝たきりになってしまいます。寝たきりになると血の巡りが悪くなり、床ずれができやすくなります。床ずれができやすいのは、頬や肘、肩甲骨、腰など骨がでっぱったところです。床ずれができると、膿んでしまうこともあり治療に時間がかかります。
からだを清潔に保つ清拭
老犬のからだは排泄物で汚れることも多いため、いつも清潔に保つことが大切です。シャンプーはからだの負担になるので、洗い流さないシャンプーや市販の体拭きなどを使って拭いてあげましょう。
お湯を絞ったタオルで拭くことも有効です。仕上げに、乾いたタオルで湿気を取り除きます。清拭は、からだの向きを変えることにもなり、床ずれ予防となります。
マッサージなどのスキンシップ
老衰になった犬には、スキンシップが効果的です。やさしく声をかけながらからだをさすり、マッサージをしてあげましょう。血行もよくなり、意識を保つ効果もあります。またマッサージをしてもらうことで、気持ちが穏やかになる作用もあります。
苦痛を和らげる
病気やケガで予後不良となった犬の場合、亡くなるまでの間も痛みで苦しむ可能性があります。動物病院には痛みを緩和する緩和ケアを実施している病院もあり、できる限り生活の質を向上させてくれます。
また、病気が重く苦しんでいる、痛みが強いなどの場合、安楽死も選択肢に入れることもあるでしょう。家族、獣医師とよく話し合うことが大切です。安楽死の際は飼い主が立ち会い、最後を見届けましょう。
いっぱい話しかける
老衰が進み意識がないように見えても、愛犬には飼い主の声が届いています。たくさん話しかけてあげましょう。聴力が落ちた子には、耳元でやさしく声をかけてください。「ありがとう」「いい子だね」などポジティブな言葉をかけるようにしましょう。
心の整理をしておく
いつかはやってくる愛犬とのお別れ。心の整理をし、準備をしていくことも大切です。考えたくないと思いがちですが、落ち着いて見送ることは愛犬のためでもあります。心の整理と準備は、ペットロスへの心の準備にもつながるものです。
愛犬の看取り方とやるべきこと
愛犬との最後をどう迎えるか、考えておきましょう。ご家族で十分に話し合うことはもちろん、かかりつけの動物病院での獣医師とよく相談します。大まかに次の3つの方法が考えられます。
動物病院・自宅で看取る
最後の最後まで治療を尽くす場合には、病院で看取ることになります。「いよいよ」というときは獣医師に連絡を入れてもらうよう、あらかじめお願いします。夜中や休診日になりそうな場合は、家に連れて帰ることも検討しましょう。
また、自宅で介護をしていた場合は、そのまま最後を看取ることになります。入院していた愛犬を引き取って最後を看取ることもあるでしょう。声をかけ、体をなでて看取ってあげましょう。
愛犬が亡くなったあとにやるべきこと
残念ながら愛犬が亡くなってしまったら、まず行わなければならないのは、自然な姿勢を取らせてあげることです。というのも、基本的に亡くなってから1~3時間後には死後硬直がはじまってしまいます。そのため、なるべく早くまぶたを閉じさせてあげたり、手足の向きなどを整えたりしてあげましょう。
その後はからだをキレイにしてあげたのち、ペット葬儀の手配をすることが必要です。最近では多くの飼い主がペット火葬を選択しています。詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:愛犬が亡くなった後にするべきこととは?あらかじめ準備をしておこう
まとめ
いつまでも幼く見えた愛犬も、いつかは老いて旅立っていきます。人間よりも愛犬と過ごす時間は短く、大変貴重と感じるかもしれません。老いを確認したらスキンシップを取り、たくさん声をかけましょう。そして無理のない範囲で、悔いのないように介護をしてください。
愛犬の最後をどう迎えるか、心の整理と準備をすることも重要です。大切な愛犬を失ったあとは、ペットロスに陥ることもあります。家族同士やかかりつけの動物病院で十分に話し合いましょう。
Last Updated on 2023/11/30 at 5:52 by ふぁみまる編集部

今まで犬を始め、フェレット・ハムスター・カメ・インコなどさまざまなペットを飼育してきました。現在は、ジャックラッセルテリアと雑種の2匹を可愛がっています。趣味は愛犬たちとの旅行です。
このメディアでは、多くの飼い主の方々の不安や疑問・困っていることを一緒に解決していきたいと考えています。