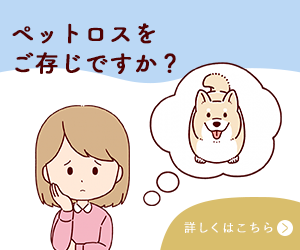老犬の夜鳴き(夜泣き)は、飼い主の睡眠不足を招くのはもちろんのこと、近所迷惑になることもあり、飼い主の大変なストレスになりかねません。夜鳴きの原因はさまざまで、認知症や痛み、お漏らし、甘えなどが考えられます。まずは動物病院に相談して、夜鳴きの原因となる病気がないか確認しましょう。同時に老犬を取り巻く環境も見直すことが大切です。
この記事では、老犬の夜鳴きについて、考えられる原因、対策や予防法について解説します。
目次
老犬の夜鳴き(夜泣き)原因は?

老犬の夜鳴きの原因には、次のようなことが考えられます。
認知症によるもの
犬にも「高齢性認知機能不全症候群」、いわゆる認知症(痴呆症)はあります。認知症の夜鳴きでは、昼間ぐっすり寝ているのに、夜になるとうろうろしながら鳴き続けるというパターンが多いようです。夜鳴きの他に、次のような症状が見られることもあります。
・いつも行っていた場所で迷子になる
・飼い主のことがわからなくなる
・狭い場所に入り込みあとずさりできない
・意味もなくグルグル歩きまわる
病気などによる苦痛や痛み
老犬になると、関節炎や変形性関節症などのの病気による苦痛や痛みから、夜鳴きをすることもあります。
不安や要求
老犬になると聴覚や視覚が衰えてくるため、周囲の状況がうまくつかめないことが増えてきます。そのため、さまざまなことで不安を覚えがちです。そこで、飼い主にそばにいて欲しい、誰かきてほしいという寂しさや要求から、夜鳴きをすることがあります。
空腹やのどの渇き
夜ごはんの時間が早いと、明け方近くに空腹を覚えて鳴くことがあります。また、体調不良や気温などの影響から、のどの渇きを感じることもあるでしょう。また、体を起こして自分で水を飲むのが大変な場合も吠えてのどの渇きを訴えることがあります。
生活環境や寝床の不快感
老犬になると、寒い環境が苦痛になります。そのため、寝床に隙間風が入ってくる、窓際に寝床があって夜の冷気でひんやりする場合など、寒さを訴えて吠えることがあります。また、老犬になると体の節々に痛みが出るため、敷物が薄い、床が硬いことも不快につながるのです。
排泄にまつわるもの
老犬になると、膀胱の収縮力が低下したり、腎機能が衰えたりと排泄の回数が増えることもあります。さらに、排泄をしたいという要求や粗相をしてしまい、その不快感から夜鳴きをすることがあるのです。
老犬の夜鳴き(夜泣き)について飼い主ができる対処法や注意点
老犬の夜鳴きが増えてきたら、次のように対処・注意しましょう。
絶対に叱らない
老犬が吠えても叱ったり叩いたりしないようにしましょう。夜中に吠えられると誰でもイライラするものですが、叱ったり叩いたりすることで、犬との信頼関係を悪化させることにもつながります。
また、叱られたとしても、「かまってもらえる」と覚えて、ますます夜鳴きをすることもあるので注意が必要です。
昼間活動させる
昼間ぐっすり寝てしまう老犬は、昼夜逆転している可能性があるため、なるべく昼間起こすようにしましょう。太陽の光に当てることで、夜眠れるようになるホルモンが分泌されます。
起きている間は、おもちゃを使って一緒に遊んだり、フードの入った知育おもちゃを利用したり、こまめに声をかけるなど心がけてください。また、簡単なおすわりやおての繰り返しも効果があります。
動画を撮っておく
夜中に鳴いている様子や、うろうろ徘徊している様子は動画に撮っておきましょう。認知症の症状かどうか、獣医師が診察で判断する際に役立ちます。
動物病院に相談する
夜鳴きの原因となるような体調不良や病気、痛みがないか動物病院を受診しましょう。認知症と思っていたら、脳に腫瘍があったというケースもあるのです。病気を治療することで、夜鳴きが治まることもあります。
また、さまざまな対策をしても、夜鳴きがどんどんひどくなるなど症状が悪化する場合は、眠れる薬やサプリメントを処方してもらえないか、獣医師に相談してみましょう。
近所に一言挨拶を
夜鳴きはご近所トラブルの原因になりがちです。近隣住民に挨拶をしておくだけでも印象が違うので、愛犬の事情を伝えるとよいでしょう。近所の人に老犬介護の経験者がいることもあるので、思いがけないアドバイスや情報、励ましをもらえる可能性もあります。
もし、近隣住民から苦情などが出た場合には、防音効果のあるペット用防音室もあるため、防音対策として検討してみてください。
生活環境を整える
老犬は、老化により身体が衰えているため、いろいろな行動が不自由になります。 例えば、老化で足腰が弱ると階段や段差を上ることが難しくなります。
また、視力が衰えると、家具などの障害物にぶつかってしまう可能性もあります。そのため、環境から段差や障害物をなくし、快適に過ごせるための介護用品を揃えてあげましょう。
寝床の場所や質を見直す
老犬の寝床の場所が夜中になると冷える、隙間風が入る、蒸し暑いなど、思いがけない原因で夜鳴きをすることもあります。外の気配が伝わってくる窓際は、老犬にとって落ち着かない場所のため寝床を移動させましょう。また、不安が強くて夜鳴きをする場合には、飼い主のそばに寝床をうつすことをおすすめします。
さらに、寝床の場所を確認したら、寝床そのものもチェックしましょう。マットは快適か、薄すぎて体を痛めていないかなどの確認が大切です。
食事や飲水の調整
明け方近くに空腹で鳴く老犬には、寝る前に何か食べさせてあげるとよいでしょう。夕方に空腹で鳴いてしまう場合には、昼食の量を減らし、夕食を多めにを食べさせるという方法もあります。
また、水を飲むための器や給水器に水がちゃんとはいっているかチェックしましょう。水飲み場を増やすのもおすすめです。寝たきりの場合には、寝る前にシリンジなどでお水を飲ませておきます。
排泄のチェック
寝る前に排泄のチェックをします。頻繁に漏らしてしまう老犬には、おむつやマナーベルトをつけてあげましょう。
たまには預けてリフレッシュ
夜鳴きが続くと飼い主も家族も介護疲れを起こしてしまいます。老犬ホームなどの施設でショートステイ(一時預かり)や、老犬を預かってくれる動物病院・ペットホテルを利用するなど、安心してプロにお任せして息抜きの時間をつくりましょう。
老犬の夜鳴き(夜泣き)を予防する方法
老犬の夜泣きを予防する方法を解説します。
生活に変化をつける
認知症の予防のために、たまにはお散歩コースを変更するなど、生活に変化をつけてあげましょう。
そうすることにより、犬の脳に刺激を与えてあげることが出来ます。
適度な運動をする
愛犬が認知症にならないように定期的に運動をさせましょう。散歩させることにより、運動や日光浴などで脳に刺激を与えることに繋がります。
また、ボールやフリスビーなどを使用した遊びも認知症予防に良いとされています。
定期的に健康診断をうける
いろいろと対策をしても夜鳴きがどんどんひどくなる、徘徊するなど症状が悪化してくることもあります。その場合は、眠れるお薬やサプリメントを処方してもらえないか、動物病院に相談しましょう。
老犬の夜鳴き(夜泣き)、、認知症?寿命との関連性
脳の変性は知能だけでなく、運動能力も低下させるため、それが余年を左右することもあります。
具体的には、四肢が動かせなくなってくると、やがて嚥下や心臓の動き、呼吸など生命に結びつく運動機能も障害されていくのです。そのため、犬の場合は個体差があるものの、発症から半年で急速に悪くなり亡くなる場合もあります。
ただ、認知症を発症するのは、犬種によってはすでに平均寿命を超えている場合も多く、認知症にならなくても、元々の余年がほとんど残されていないのが現実です。
まとめ:老犬の夜鳴き(夜泣き)を乗り切る

老犬の夜鳴き(夜泣き)は飼い主の寝不足を招くだけでなく、近所迷惑にもなり、飼い主にとって大きなストレスになります。老犬の夜鳴きには、認知症以外の病気が原因の可能性もあるので、まずは動物病院を受診しましょう。
そして、老犬の寝床が快適か、空腹ではないかなどを確認すると同時に、昼間は太陽に当てたり、遊んであげたりとなるべく起こして活動させることも大切です。それでもなかなか治まらない場合は、動物病院に相談し、サプリメントや薬の処方も検討してみてください。