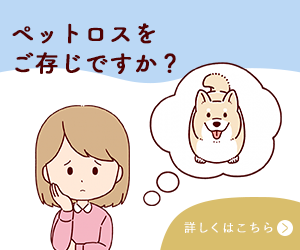たまたま愛犬のおへそを見たときにでべそな気がして、問題ないのか不安になっている飼い主もいるのではないでしょうか。
この記事では、犬がでべその場合に考えられる原因や症状、治療法などについて解説します。
目次
犬のでべそは病気なの?
そもそも犬のでべそは、病気なのでしょうか。
ここでは考えられる病気やでべそになりやすい犬種を紹介します。
でべそはお腹のヘルニア
「ヘルニア」というと、椎間板ヘルニアをイメージされる方が多いと思います。
しかし、ヘルニアとは、臓器や組織などが本来あるべき位置から飛び出してしまった状態のことです。そのため、ヘルニアの中でも「臍(へそ)」の部分から脂肪や腸などが飛び出ている状態は「臍ヘルニア」といわれます。
犬のおへその部分が出っ張ってでべそのようになっている場合、この臍ヘルニアを引き起こしている可能性があるのです。
臍ヘルニアとは、おへその部分から臓器や組織などが皮膚の下に突出する病気のことを指します。
臍ヘルニアになりやすい犬種
臍ヘルニアの好発犬種には、ペキニーズ、シーズー、エアデール・テリア、キャバリア、アメリカン・コッカー・スパニエル、秋田犬、ワイマラナーなどがいます。これらの犬種を飼っている場合は、より注意が必要です。
ただしこれら以外の犬種でも、臍ヘルニアを発症してしまうリスクはあるため、愛犬がでべそのようなら、動物病院を受診しましょう。
臍ヘルニアの原因は?

臍ヘルニアには「生まれつきのもの」と、「成長してからできる後天性のもの」の2つがあります。それぞれどのような原因が考えられるのでしょうか。
生まれつきのもの
妊娠中、子宮の中の仔犬が母親から酸素や栄養をもらうため、子宮の中では胎盤と仔犬が臍の緒(臍帯)によりつながっています。臍帯は、仔犬のお腹の穴の開いている部分から体内に入り込んでいるのです。
通常、生まれて不要となった臍帯は乾燥して落ち、仔犬のお腹の穴は自然と閉じて臍になります。しかし、穴がうまく閉じなかった場合、そこから臓器や組織が突出し臍ヘルニアになるのです。
後天性のもの
激しい運動や肥満、避妊手術後に縫い目が閉鎖しなかったなど、稀に後天的な原因で臍ヘルニアを発症することもあります。
臍ヘルニアの症状は?
犬の臍ヘルニアは、穴の大きさや、突出している臓器や組織によって症状が異なります。
還納性臍ヘルニア(かんのうせいへそヘルニア)
穴が小さくて、突出しているものが脂肪であれば、見た目もでべそ気味な程度です。このような見た目の臍ヘルニアは、還納性臍ヘルニアと言います。また、突出部分を押すとおなかの中に引っ込むケースや、仰向けに寝ると突出がなくなるケースもあり、痛みもほぼありません。
嵌頓性臍ヘルニア(かんとんせいへそヘルニア)
突出した臓器の一部がヘルニア門に挟まり込んで、押しても腹腔内に戻らなくなった状態を嵌頓(かんとん)と言います。
嵌頓性臍ヘルニアになると、突出した臓器の血行が悪くなるため、激しい痛みや食欲不振などの症状があらわれることが多いです。
また、臓器が子宮や腸管などであった場合には、嘔吐や下痢などが症状としてあらわれます。
絞扼性臍ヘルニア(こうやくせいへそヘルニア)
ヘルニア門の締め付けが強いと、腸などに血が通わなくなってしまい、このような状態を絞扼(こうやく)と言います。
また、絞扼により腸へ流れる血液が止まると、その部分が壊死しまう場合もあります。
絞扼の症状としては、持続的な腹痛や、腸閉塞、腸破裂、敗血症、ショックなどがあり、絞扼の状態が長く続くと、命の危険性もあります。
小さく柔らかいでべそでも手術は必要?治療法と費用について

通常、臍ヘルニアは、生後6か月頃までに自然的に治るものが多く、この時期まではそのまま放置していても問題はありません。
しかし、生後6か月を過ぎても治らない場合には、手術が必要となるケースがあります。
還納性臍ヘルニアの場合の治療
還納性臍ヘルニアの場合は、それほど極端に大きなヘルニアでない限り、ヘルニアの内容物をお腹の中に戻した後に腹膜を縫合するという比較的簡単な手術になります。
嵌頓性臍ヘルニアや絞扼性ヘルニアの場合の治療
開いてしまっている穴が大きいため、糸で縫い合わせて閉じるのではなく、人工補強材(メッシュ)を使って閉じる方法が用いられる場合があります。また、腸などが壊死してしまっている場合には、壊死部分を切除する手術も同時に行う場合もあります。 また、臍ヘルニアが小さい場合には、避妊や去勢手術の際に一緒に臍ヘルニア手術を行う場合が多いようです。
臍ヘルニアの手術費用は?
手術を行う場合には、ヘルニアの状態によって治療費に違いがありますが、手術費や入院費を含めて、20〜30万はかかると考えておきましょう。
まとめ
犬の臍ヘルニアは予防できる方法がありません。早めに対応し重症化しないことが大切です。
日頃から愛犬の様子をよく確認したり、動物病院で定期検診を受けることで、早期発見、早期治療に努めましょう。
Last Updated on 2024/03/05 at 5:16 by ふぁみまる編集部

今まで犬を始め、フェレット・ハムスター・カメ・インコなどさまざまなペットを飼育してきました。現在は、ジャックラッセルテリアと雑種の2匹を可愛がっています。趣味は愛犬たちとの旅行です。
このメディアでは、多くの飼い主の方々の不安や疑問・困っていることを一緒に解決していきたいと考えています。