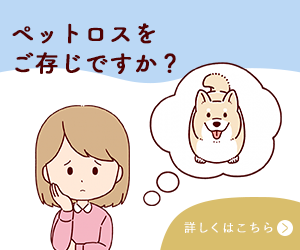大切な家族の一員であるペットが亡くなってしまった際、悲しみに暮れてしまい、様々なことに手がつかないこともあると思います。しかし、そんな中でも場合よっては公的な手続きが必要な場合もあります。
手続きによっては死亡から何日以内という規則があるため早めに手続きが必要です。そのため、必要な書類の準備や、手続きの手順を把握しておけばスムーズに手続きが進められます。
本記事ではペットが死んだら速やかにすべき手続きや、その方法について詳しく解説していきます。

目次
ペットが死んだ場合に必要な手続きとは?
ペットが死んだ場合に必要な手続きはペットによっても異なりますが、犬の場合は手続きがとくに重要です。原則として死亡届の提出が義務付けられており、30日以内に所定の提出先に死亡届を出さなければなりません。
提出先は地方自治体によって異なりますが、市役所や保健所、または環境衛生課に提出しましょう。提出方法も異なる場合がありますが、該当窓口への提出ならほとんどの場合で問題ありません。提出時には犬の登録鑑札などが必要になります。
犬の死亡届の提出は任意ではなく義務のため、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
猫の場合は法律で定められた登録義務はないため、死亡届の提出は必要ありません。ただし、犬と猫の場合はマイクロチップの登録を行っている場合に登録情報の抹消が必要です。
その他のペットの場合は死亡届や登録抹消は必要ありませんが、ペット保険に加入している場合は解約しましょう。解約をしないと毎月の支払いが続いてしまいます。
ただし、犬や猫以外であっても大型のペットや、人に危害を加える可能性があると指定されている特殊なペットの場合は自治体によって届け出が必要と指定されている場合があります。あまり一般的ではない大型のペットや飼育に注意が必要なペットを飼っている場合は自治体に確認をしてみましょう
ペット保険によっては死亡時の葬儀費用や仏具費用が出る場合もありますが、その場合は死亡診断書が必要になりますので、動物病院で診断書を出してもらいましょう。
愛するペットが亡くなった後に様々な手続きをしないといけないのはつらいかもしれませんが、とくに犬の場合は届け出義務がある手続きなので、必ず行うようにしましょう。
ペットが死んだ場合に提出が必要な書類
ペットが死んでしまった場合、ペットに応じた手続きが必要です。とくに犬の場合は死亡届の提出が必須ですので、必要な書類をまとめて必ず提出しましょう。
各種の届け出の際に必要な書類をまとめましたので参考にしてください。
死亡届
ペットの犬が亡くなった場合に死亡届は必須ですが、その際に必要な書類は以下の通りです。
- 死亡届
- 狂犬病予防注射済票
- 登録鑑札
登録鑑札は書類ではなくプレート状の金属タグですが、届け出の際には必須ですので必ずもっていきましょう。
死亡届は該当する窓口だけでなく、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあるので、可能であればダウンロードして自分でプリントし、先に記載しておくのがおすすめです。
死亡届の提出には飼い主の情報や愛犬の情報と亡くなった日などを記載する必要があるので、窓口で死亡届をもらって現地で記載する際に慌てずにすむようにまとめておきましょう。また書類には印鑑も必要ですので、忘れずに持っていきましょう。
死亡届は愛犬が亡くなってから30日以内と定められている自治体もありますので、期日には注意しましょう。
また、一部の特殊なペットの場合は、自治体によって届け出が必要なペットの種類や届出方法が異なるため、保健所や地方自治体に問い合わせましょう。
血統書登録の抹消の手続き
亡くなった愛犬が血統書団体に加入している犬だった場合、血統書の登録抹消手続きが必要になります。必要な書類は以下の通りです。
- 血統証明書の原本
- 死亡届用紙
血統証明書はコピーではなく、必ず原本を提出しましょう。愛犬との思い出として血統書を取っておきたい場合は、コピーを手元に残し、原本を提出するのがおすすめです。死亡届は地方自治体に提出するものと同じです。
抹消には死亡届と同じように飼い主の情報や、亡くなった愛犬の情報が必要になります。自治体に死亡届を提出する際に同じものをもう一部用意しておきましょう。
血統書登録の抹消は法的に必須ではありませんが、トラブル防止のために手続きをおこなっておきましょう。
死亡診断書
ペット保険に加入している場合、ペットが死亡した場合の保険金をもらう場合や、解約をするのに死亡診断書が必要になります。
保険会社にもよりますが、提出は郵送または保険会社のホームページで可能な場合があります。提出形式も調べておくとスムーズに解約を進められます。
マイクロチップの登録解除
亡くなったペットが犬か猫の場合でマイクロチップの登録をしている場合は、登録の解除が必要です。これは地方自治体に提出する死亡届とは別の手続きになります。
地方自治体に死亡届を提出しても地方自治体で死亡届と鑑札および注射済票の返納が必要です。
マイクロチップの登録解除は環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にある「死亡などの届出」から解除の届け出が可能です。マイクロチップの登録解除は基本的にペットが亡くなってから30日以内にする必要がありますので注意しましょう。
ペットショップで購入した場合は、販売時にマイクロチップの装着が義務付けられているのですでに登録されています。
登録解除時に必要なマイクロチップの識別番号と暗証記号は登録証明書に記載されています。登録証明書を紛失してしまっている場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で再交付の手続きを行いましょう。
環境省:犬や猫の飼い主の手続き一覧(犬と猫のマイクロチップ情報登録)

ペットが死んだ場合における市役所手続きの流れ
ペットが死んだ場合、ペットによっては市役所などの地方自治体で死亡届を提出する必要があります。場合によっては提出先が市役所ではなく、保健所などの場合もありますので、該当する地方自治体のホームページを確認しておきましょう。
ここでは基本的な死亡届提出の流れを詳しく解説していきます。
①必要書類の用意
死亡届を提出する際には死亡届の書類だけでなく、狂犬病予防注射済票と登録鑑札が必要になります。死亡届自体は提出する窓口でもらうか、地方自治体のホームページからダウンロードして印刷して用意しましょう。
犬鑑札や狂犬病予防注射済票をなくしてしまっている場合でも手続きは可能で、死亡届内の鑑札や注射済票の返却で紛失と記載しておけば問題なく受理される可能性はあります。
本来は返納すべきものですので、愛犬との思い出としてとっておきたい場合でもまずは窓口に相談してみましょう。鑑札や注射済票の紛失に罰則はありませんが、故意の場合は狂犬病予防法違反になる可能性があります。
特殊なペットの場合は別の届け出が必要な可能性がありますので、問い合わせておくのがおすすめです。
②死亡届の記入
犬の死亡届に記入する内容は大きく分けると飼い主の情報と亡くなった犬の情報の2つです。
飼い主の情報は住所氏名や電話番号などの連絡先ですが、記入が必要な亡くなった犬に関する情報は以下の通りです。
- 犬の名前
- 登録番号
- 犬種
- 毛色
- 性別
- 生年月日
- 死亡日
- 死亡理由
- 鑑札・注射済票の返却
死亡届の用紙は窓口でもらえるため直接出向いた際に記入もできますが、あらかじめわかるようにしておくとスムーズに記入ができます。
地方自治体によってはWebサイトからダウンロードできる場合もありますので、可能であればダウンロードして記入するのがおすすめです。場合によっては届け出用のフォームから電子申請も可能です。
③死亡届の提出
死亡届の提出は地域によって異なりますが、市役所や保健所などが窓口になっていますので、お住いの地域の情報を確認しましょう。
窓口の場合は公的機関ですので平日日中が受付時間となっているため、提出が難しい場合もあります。郵送や電子申請が可能であればそちらを利用するのがおすすめです。
ただし、記入に不明点がある場合や、聞いておきたいことがある場合は直接窓口で確認をしてから死亡届を提出するようにしましょう。
特殊なペットの場合は届け出の書式や届出先が違う場合もありますので、該当する自治体のホームページを確認しておきましょう。
ペットが死んだら手続き以外にも葬儀の準備が必要
愛するペットが亡くなってしまった場合、死亡届などの手続き以外にも葬儀など供養も検討しましょう。家族の一員として一緒に暮らしていたのであれば、悔いのないように見送ってあげるのがおすすめです。
とくにペットの遺体は市などに委託する場合は供養ではなく処分扱いになってしまう可能性もあるため、しっかりと供養できる火葬がおすすめです。自宅の庭などに埋めるつもりであっても、衛生面や近隣への影響も考えられるため火葬後に埋葬しましょう。
ペットの葬儀業者は多いですが、費用だけで比較せず、実績や口コミなども考慮して選ぶようにしましょう。その際に注意してみておきたいポイントは以下の通りです。
- 創業から数年以上経っている会社か
- 料金が適正かどうか
- 葬儀のスケジュールがはっきりしているか
- 企業ホームページ以外でも口コミ評価が良いか
- 電話やメールの対応が良いか
ペット葬儀業者の公式サイトだけでなく、外部に掲載されている実際に利用した人の口コミ評価は参考になります。安すぎる料金やずさんな対応など、どこか不審に感じる部分がある業者は避けた方が良いでしょう。
また、返骨や分骨を希望している場合は個別火葬をしてくれるかどうかや、粉骨のサービスがあるかも選ぶポイントになります。分骨カプセルや遺骨ジュエリーを利用して、亡くなったあとも愛するペットを身近に感じていたいという人は、粉骨サービスを利用するのがおすすめです。
それ以外にメモリアルグッズとして、フォトフレームや仏具などを取りそろえている業者もありますので、気に入ったメモリアルグッズがあれば検討してみましょう。

ペットが死亡した際の手続きに関するよくある質問
ペットが死亡した際の手続きは本記事で紹介したようにいくつかありますが、それらに関するよくある質問をまとめました。
ペットの死亡届を出さないとどうなりますか?
犬の場合は死亡届の提出が義務となっており、狂犬病予防法違反に該当する可能性があります。故意に届け出を怠ったと判断された場合は罰金を科される可能性もあります。
死亡後は30日以内に必ず死亡届を提出するようにしましょう。
犬以外のペットの場合は基本的に死亡届を提出する必要はありませんが、危険動物や特定外来生物などの場合は届け出が必要な可能性もあるので該当する地方自治体に問い合わせてみましょう。
ペットの火葬には死亡診断書が必要ですか?
ペットの火葬時に死亡診断書は基本的に不要です。ただし、死亡診断書を求められる場合もあるので、その場合は動物病院で死亡診断書を出してもらいましょう。
死亡診断書は2,000円~3,000円程度かかるのが一般的なので、あらかじめペット火葬業者に必要かどうかを確認しておくのがおすすめです。
かかりつけの病院があれば、死亡診断書にかかる費用をあらかじめ確認しておくとスムーズです。
ペットを自宅の庭に埋葬しても大丈夫ですか?
自分の所有地であれば問題ないケースが多いですが、衛生面や水質汚染の影響を考慮して埋葬する必要があります。公共の場所や他人の土地に埋葬すると違法となる可能性が高いので注意しましょう。
トラブルを避けるためにも、可能であれば火葬してから埋葬したほうがトラブルになりにくいといえます。
火葬後に骨壺に修めて供養したり、分骨カプセルなども利用できるため、愛するペットの供養方法としてもおすすめです。
まとめ
本記事ではペットが死んだら必要な手続きについて詳しく紹介しました。死亡届が必要なのは犬だけですが、マイクロチップの登録をしている犬・猫は登録の解除が必要です。
公的な手続き以外ではペット保険の解約や血統書登録の抹消などもありますので、義務ではありませんが、該当する場合は忘れずに手続きを行いましょう。
また、供養のためにも亡くなったあとは火葬がおすすめです。信頼できる業者に依頼し、愛するペットを見送ってあげましょう。
Last Updated on 2025/05/27 at 3:46 by ふぁみまる編集部